Webなんでも鋳物館 鋳物の歴史
第2章 技術革新の軌跡 2. 大砲・鋳鉄橋(その1)
大砲の鋳造と反射炉
1543年(天文12年)ポルトガル船がわが国最南端の地種子島に漂着した。これをきっかけに日本とポルトガル、ついでオランダとの間に交易が開け、徳川幕府によって鎖国令の出された1635年(寛永12年)までの100年ほどの間であったが、ヨーロッパとの交流が行われた。この時期の最大の収穫は、鉄砲の入手とこれを手本に大阪の堺と近江の国友村で鍛冶師たちによって鍛造の鉄砲がつくられたことであろう。特に近江国友の鉄砲鍛冶は秀吉や家康に保護され、やがて徳川幕府の砲兵工廠的な役割を果たした。
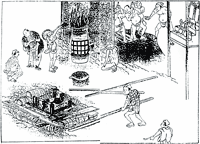
図1:源保重による「大筒鋳之図」
江戸時代の溶解炉「甑」[こしき]と炉に風を送る「踏鞴」[たたら]、手前に大砲の砲身の鋳型が床に埋めてあり、甑で青銅を溶かしこの鋳型に鋳込む
1600年代になると青銅鋳物の大砲もつくられるようになった。ヨーロッパでは先込式の青銅砲が既につくられており、砲身は中子を入れて中空の鋳物とし、内面を切削して完成している。わが国でも同様の製作法が採られたようで、この工程を図解した源保重による「大筒鋳之図」[おおづついこみのず](1847年)がある。(図1参照)

写真1:韮山の反射炉
高さ約16m、1号炉が1854年(安政元年)完成

写真2:萩の反射炉
高さ約12m、1858年(安政5年)完成
江戸末期の弘化・嘉永(1844~1854年)のころになると先進諸国の開国要求や圧迫を受け、国防の必要からますます大砲の製作が活発になり、1855年(安政2年)には寺院の鐘を大砲に鋳直すことが指令され、仏像の鋳造が禁止された。また、青銅より強度の高い鋳鉄で大砲をつくることが試みられたが、従来鋳鉄溶解に用いられてきた溶解炉「甑」[こしき]では砲身を鋳込むほど大量の溶湯を一度に供給することが困難であること、および溶解過程での炭素の吸収が大きく、材質が軟らかくなるといった理由から溶解に反射炉を使用しようとし、各地にその建設計画が進められた。
まず1850年(嘉永3年)佐賀藩が「築地大銃製造方」2基4炉の反射炉を築造し、1853年には「多布施公儀石火矢鋳立所」を増設して鋳鉄製大砲の製造に乗り出した。その後、1864年 (元治元年)までの15年間に鹿児島・韮山・那珂湊(水戸)・六尾(鳥取)・萩(長門)・大多羅(岡山)などにも反射炉が建設された。(写真1,2参照)
このように鎖国政策のもと、わずかに開かれていたオランダから1836年(天保7年)にUlrich Hugueninの書いた技術書「ロイク王立鉄製大砲鋳造所における鋳造法」(Het Gietwezen in's Rijks Ijzer ─ geschutgieterij te Luik 1826年出版)は、産業革命以来発展した近代科学技術を伝える唯一のヨーロッパ技術の手引書であり、反射炉の築炉や砲鋳造の技術だけでなく、高炉の構造や鉄鉱石の精錬など鉄冶金全般について記述されており、わが国の製鉄・鋳造技術近代化に大きな役割を果たした。
【アイシン高丘30年史掲載「鋳物の歴史」石野亨執筆より抜粋】